


UMIUMA JOURNAL 
東日本唯一の干しカレイ専門店として、手作りの味を大切に。
三陸・宮古の風土と山陰の技が融合。
岩手県のほぼ中央、本州最東端に位置する宮古市。1615年に開港した天然の良港・宮古港には豊富な魚介が水揚げされ、漁業の町として栄えてきました。この港町で、「東日本唯一の干しカレイ専門店」として、三陸や北海道のカレイを原料にした商品を展開しているのが「宮古マルエイ」。今回は会社や地域のことなどについて、総務・営業・品質管理部長の稲村千佐喜さんに話を伺いました。

「宮古マルエイ」は、宮古市で主にイカの加工を手掛けていた株式会社大濱正商店と、島根県で輸入かれいの干物を手掛けていた株式会社マルエイにより、1994年に設立されました。宮古港から車で10分ほど、すぐ脇を閉伊川が流れる同社の立地は、北日本の主要なカレイ産地に近く、乾いた冷たい風が吹くため、干物づくりに最適。さらに早池峰山系の良質な地下水にも恵まれています。「岩手では珍しく軟水で雑味が入りにくいため、素材の味を活かしたい干物にぴったりです。水質を分析した専門家の方も『いい水ですね』と言ってくれました」と稲村さんは話します。

また、この水をふんだんに使って行われる下処理は“山陰流”。「山陰のやり方にならって、うろこ取りや汚れの除去を徹底的に行っています」と稲村さん。この下処理により干物はくさみが抑えられ、中まで均等に味が入り、塩角のないまろやかな味に仕上がります。宮古マルエイでは、マガレイやソウハチといった全国的によく食べられるものから、サメガレイといった宮古ならではのものまで、さまざまなカレイを取り扱っています。


こうして作られる商品は銀座の百貨店にも並べられるほど、評判でした。しかし、その状況を一変させたのが2011年の東日本大震災。同社では津波被害は免れたものの停電や凍結設備配管が破損。連絡手段も限られる中、物流が停止し、出荷もままならない状態に。また、原発の風評被害にも悩まされ続けましたが、そのような状況の中でも稲村さんのお母様で取締役の晴美さんは前を向き、商談会や講演会などに積極的に足を運んでいました。
しかし、2016年の台風10号で再び被災。工場は1.3mほどの高さまで浸水し、設備機器が損壊しました。その状況を見て、当時東京のメッキ会社の品質管理部門で働いていた稲村さんは帰郷することを決断しました。「私にも何かできるのではと思い、『もう会社を畳もうか』という話をしていた両親を『一緒にやらせてほしい』と半年ほどかけて説得し、正式に入社しました」。
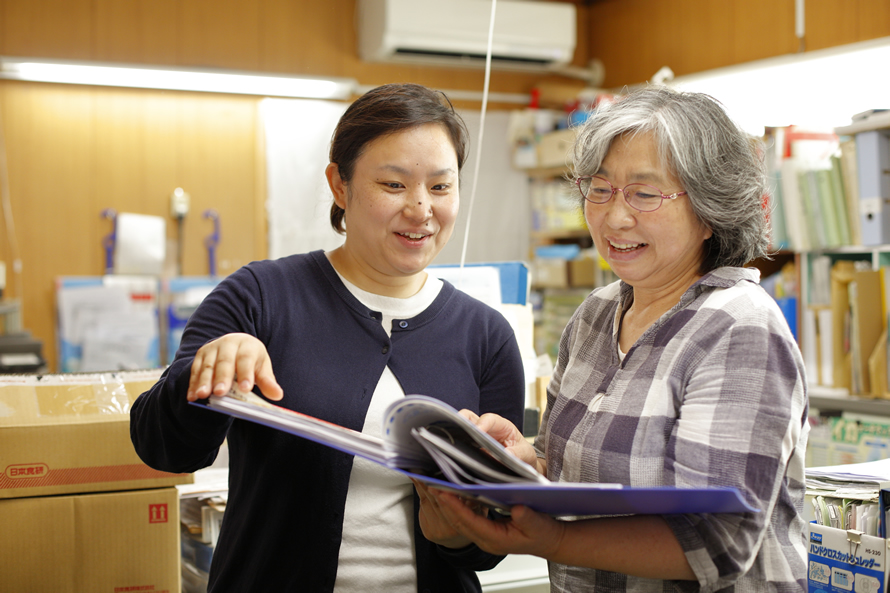
一人でも多くの人にカレイのおいしさを。
前職で品質管理や分析を行っていた稲村さんは入社後、食品衛生管理規格のHACCP(ハサップ)に準じた衛生管理実施工場認定を取得するなど、生産現場や受注システムを整備。さらに「会社の顔が見えるように」とブランディングに取り組み、ホームページ、チラシやパンフレット、商品のラベル作りなどにも挑戦しています。

また、近年は県内外のメーカーや店舗などとコラボレーションし、カレイが丸ごと入った「魚拓せんべい」やミールキットといった商品展開も積極的に行っています。その理由について稲村さんは「若い世代が魚を食べるきっかけになる商品を作りたかったんです」と説明しました。「骨を取るのが大変、可食部が少ない、内蔵が苦いなど、魚を食べない理由は人それぞれです。ただ、味が嫌いという人はほとんどいないので、それらの課題を解決して、一度口にしてもらえる商品を目指しています」。

さらに現在は宮古の水産業を盛り上げようと、地元の業者2社と手を組み、共同での商談会や商品開発なども行っています。「本州最東端にある宮古市は“日本一日の出が早い”とも表現できるので、“朝ごはんがおいしいまち”というコンセプトで、新しいコラボ商品も開発中です」。

近年、原料となるカレイの確保が不安定になる中、それでも稲村さんは「私たちは頑固にカレイ一筋でやっていきます」と語ります。「以前は『カレイしかないね』と言われたこともあったのですが、それでもやり続けることで高い信頼を築けました。これまでの商品を愛してくれている人、そして一人でも多くの人に喜んでほしいという想いで、これからも手作りの味を大切にしていきたいですね」。
COMPANY INFO 今回のつくり手さんの会社

有限会社宮古マルエイ
- 住所
- 〒027-0044
岩手県宮古市上鼻2-1-33 - 取扱製品
- かれい(ヒレグロ、ソウハチ、ミズカレイ、サメカレイなど)、⼲かれい、煮付け商材、かれい加⼯品 ほか
